【2025年7月の記録】
早いもので、初診から半年。
この日は「国立循環器病研究センター(国循)」での2回目の診察日でした。
前回と同じく妻と二人で車に乗り込み、大阪へ向かいます。
「早く終わったら、ららぽーとエキスポシティで買い物して帰ろうか」
――そんな軽い気持ちで出発したのを、今思えば少し恥ずかしく感じます。
まさかその日が、衝撃の1日になるとは想像もしていませんでした。
国循での再検査
この日の検査はCT、レントゲン、心エコー。
今回のCTでは造影剤を使わないので気楽なものです。
しかし、心エコー検査が始まると、いつもと違う空気を感じました。
技師さんが何度も入れ替わり、モニターを覗き込みながら何やら話し合っています。
隣の部屋ではヒソヒソと相談の声。
検査時間もいつになく長い。
ベッドの上で冷たいジェルに触れながら、「もしかして何か良くない結果なのか?」と、心の中がざわついていきました。
ちなみに、院内は空調が強く、検査室は真夏でもむしろ寒いです。心エコー室で上半身裸で長時間検査を受けたら体は冷え冷えに。
これから行かれる方は、羽織れる上着を一枚持っていくと安心ですよ。
運命の診断結果
すべての検査を終え、いよいよ主治医との面談。
僕の心臓の映像と数値を前に、先生は静かに口を開きました。
「かなり症状が進んでいますね。体、しんどくないですか?
普通なら息切れや動悸が出てもおかしくないですよ」
耳に入った言葉の意味を理解するまで、少し時間がかかりました。
自覚症状がないだけで、病状は確実に進行していたのです。
そして続く言葉――
「2〜3ヶ月以内に手術が必要です。いつにしますか?」
その瞬間、目の前がスッと暗くなりました。
妻も僕も言葉を失います。
覚悟はしていたつもりでしたが、「その時」がこんなにも早く訪れるとは。
ただ、先生の口調は驚くほど穏やかでした。
重い宣告のはずなのに、不思議と安心感すら覚えるほど。
その落ち着きと自信が、経験豊富な心臓外科医の風格を感じさせました。
「この先生に任せれば大丈夫だ」
そう思えることが、どれほど心強かったか。
半年で進行した診断結果
2025年1月とこの度7月に受けた心臓超音波検査(心エコー)の結果を比べると、この半年で大動脈弁閉鎖不全症の進行がはっきりと見えてきました。
心臓が少しずつ大きくなり、ポンプの力も弱まってきている状態です。
僕の結果の一部は以下の通りでした。
| 項目 | 1月 | 7月 | 説明 |
| 左室拡張末期径(LVDD) | 59 mm | 63 mm | 心臓が血液を受け入れるときの大きさ。逆流で拡張。 |
| 左室収縮末期径(LVSD) | 40 mm | 47 mm | 収縮後も血液が残りやすくなり、機能が低下 |
| 駆出率(EF) | 63% | 58% | ポンプ力を示す数値 |
| 短縮率(FS) | 40% | 25% | 心室の動きが弱くなってきている |
| 大動脈弁逆流(AR) | 中等度 | 中等度~重度 | 逆流の勢いが強まっている |
1月の時点では「中等度の逆流」でしたが、7月には心臓の拡張が進み、逆流量も増加。
心臓の筋肉が徐々に疲れてきていることを示す結果でした。
医療的に見ると、
- EF(駆出率)58%
- LVSD(収縮末期径)47mm
この辺りの数値が、手術を検討し始める目安に近づいているようです。
つまり、心臓が逆流を補いきれなくなり始めているサインといえます。
わかりやすく言うと、
半年前までは、逆流があっても心臓が元気にカバーできていた。
今は、負担が積み重なり、少しずつ心臓が大きく、押し出す力も弱まってきている。
この結果を見て、症状の進捗速度を考えると2〜3ヶ月以内に手術をすべきと判断されたようです。
手術の選択肢
先生が説明してくれた手術方法は3つありました。
① 自己弁修復術
自分の大動脈弁を修復して温存する方法。
体への負担も少なく、薬も一時的で済む。ただし、弁の状態によっては修復できないことも。
② ロス手術
自己弁の修復が難しい場合に、大動脈弁を取り除き、自分の肺動脈弁を大動脈側に移植する高度な手術。
肺動脈弁の代わりには、冷凍保存された他人の弁を使用します。
手術時間も長く、心臓を止める時間も長いので体への負担も大きいが、予後を考えると若年層に向いた術式とのこと。
③ 人工弁置換手術
人工弁(生体弁や機械弁)を使うオーソドックスな方法。
ただし機械弁を選ぶと、一生「ワーファリン」という薬を飲み続けなければなりません。
ケガや鼻血にも気を使う生活になりますし、一生行動に制限がかかってしまいます。
大抵の病院では③の一択になってしまいます。
しかし、国循は①や②のような“自分の弁を活かす手術”が可能な、国内でも限られた病院のひとつ。
僕が大阪まで通っている理由も、まさにそこにあります。
「自己弁修復が難しい場合はロス手術でお願いします」
そう伝えた瞬間、胸の奥にスッと覚悟が宿りました。
あとは先生に全てを託すのみです。
手術日を決める
季節は7月。
仕事の段取りをつけるのと、子どもが家にいる夏休みは避けたいため、9月上旬に手術日を決めました。
あと2ヶ月。準備期間は意外と短い。
その後も入院の手続き、各種検査、歯科受診、説明など。
本来なら「ららぽーとで買い物して帰る」予定が、病院で夕方まで過ごすことになりました。
帰りの車の中では、妻と「入院前中のこと」「子どもたちのこと」をひとつずつ話し合いながら、
少しずつ“現実”を受け止めていきました。
心臓を一度止める――
そんな大手術が、自分の体に行われる。
頭では理解していても、実感が追いつかない。患者本人しか分からない不安は決して拭えるものではありません。
けれど、もう立ち止まれない。
あの日の帰り道、窓の外に沈む夕日を見ながら、
「この手術を乗り越えて、もう一度あの光を見よう」
そんな思いが、静かに胸の中に灯りました。

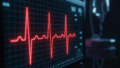

コメント